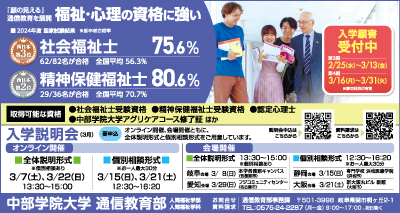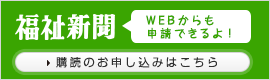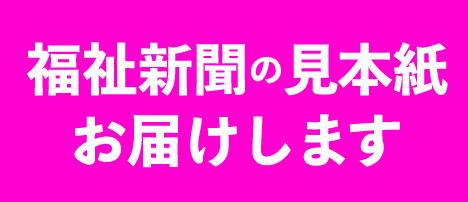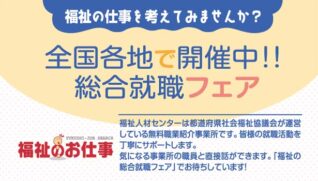社会福祉法人風土記<14>青垣園 上 「必ず光るものはある」を信念に
2016年08月08日 福祉新聞編集部
「やまと(倭)は 国のまほろば たた(畳)なづく 青垣 山ごもれる やまとしうるは(美)し」(大和はすばらしい国、幾重にも重なる垣根のような山々に囲まれた美しいところだ)
8世紀に編まれたわが国最古の歴史書「古事記」に残る歌である。詠んだのは東征の帰途に亡くなったヤマトタケルノミコト。今も変わらぬその山影を映して流れる葛城川のほとり、奈良県大和高田市に社会福祉法人「青垣園」は建つ。
環濠集落の名残りをとどめる周辺の緑はまだ濃い。
救護施設(定員110人)、指定障害者支援施設(同120人)、そして福祉ホーム(同10人)を運営する。「利用してよかった」と心から思えるサービスを−これが法人の精神だ。「民間サービスのノウハウは進んでいる。どんどん採り入れたい」。一昨年秋、第9代の法人トップとなった松岡文男理事長(63)は言う。
元奈良県職員という役人出身とは思えぬ柔らかな発想である。施設が県営で発足、職員の処遇面も恵まれた条件にふさわしいサービスの質を目指す決意がにじむ。
■恵まれた公営施設
園は1959(昭和34)年、財団法人として許可された。岩戸景気(昭和33~36年)の陰で生活に苦しむ障害者らが目立ち始めた頃である。県の出資と篤志家からの土地の寄付だ。さらに大和高田市からの借地で広がった翌1960年、社会福祉法人へ衣替えした。
とかく〝親方日の丸経営〟とやゆされがちな公営施設だが、歴代役員の努力の中で第4代の故・巽曻園長(1920~2009年)の取り組みは特にユニークだった。戦前、奈良県庁に入り、事務部門などを歩いた。戦後、視覚障害者の暮らす県平城寮勤務(副寮長)のあと1969(昭和44)年、青垣園長へ。ときに49歳。
以来、顧問となって身を引く1985(昭和60)年までの16年間、相次いで新設、経営を委託された県立青垣授産所(昭和52年)、同青垣更生園(同53年)のそれぞれ初代責任者も兼ね、法人の礎を築いていく。経営の厳格化を掲げて救護施設や青垣更生園に複式簿記を適用(同52年)したのもこの頃である。
「障害はあっても人である以上、必ず光るものはある」
これが巽園長の口ぐせだったという。だが、その力をどう引き出していけばよいのか。
■土の温もりとともに
授産作業は幅広い。一見優しく、怒ると怖い小柄な巽園長が発案したのは陶芸。土鈴を手作りして売り、利用者の社会参加へつなげようとのアイデアだ。一度失敗したら元へ戻らぬ木工などと違い、粘土の造形はやり直しがきく。それに土の温もりには、人の心に響く何かがある。

酉の土鈴を作る陶芸班
とはいえ、作陶の知識を持つ職員などいない。地元の画家、窯元、彫塑家らを訪ね、担当職員はイチから学んだ。1981年には3段の本格的な登り窯まで園の一角に新築した。ここまで徹底する施設は少ないと言えよう。
「できたよ!」
一つ作業をクリアし、あるいは作品が仕上がるたびに歓声を上げる利用者たち。職員に駆け寄り、見せにくる光景も珍しくなかったという。製作に加えて販路開拓という、これまた慣れぬハードルは控えていたが、平成になって始まる野菜づくりともども、利用者と「土」との触れ合いは深まっていった。