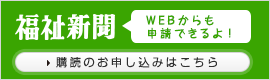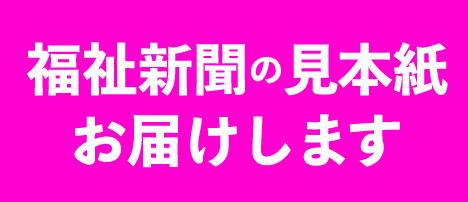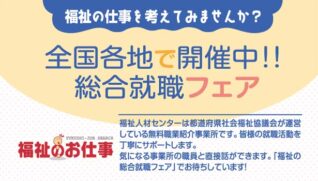社会福祉法人風土記<18>仙台キリスト教育児院 中 子育てのあり方 模索し続ける
2016年12月19日 福祉新聞編集部
「子は親の鏡」ならば、「児童養護施設は時代を映す鏡」と言える。
東北を襲った大凶作による飢餓児童の救済活動をきっかけに1906(明治39)年、「仙台キリスト教育児院」は創設された。
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という聖書の言葉を基本に110年、精神は変わらずに来たが、入所児童は時代と共に変わってきた。
三陸海岸大津波(1933年)や敗戦(1945年)による混乱が続き、そのつど災害孤児、戦災孤児、浮浪児といった“時代の落とし子”が次々と育児院にやってきた。高度経済成長を経て、バブル経済に沸く1980年代からは親による虐待が入所理由の上位を占めるようになった。
「家庭のぬくもりの中で育てたい」との理想の下、育児院も子育てのあり方を模索し続けてきた。
今年、社会福祉法人の10代目院長となった鈴木重良・丘の家子どもホーム園長(67)は、1974年に正規職員になってから常に子どもと接してきた。若き日を振り返る。
「小学校に入る前、未就学児に健康診断やテストがありました。先生が絵を見せて、『これはフライパンです。足りないものを書き加えてください』と問題を出す。丸く描かれたフライパンに取っ手を付けるのが正解で、家庭で親のいる子は取っ手を書き加えたのに、育児院の子は分からない。日常生活の中ではフライパンを見たことがなかったからです。日ごろ、子どもが入れない厨房で専門職員によって作られた食事を食堂で食べる、という生活だったからです。これではだめだ。もっと子どもたちを一般家庭に近づけましょうと私は主張しました」
紆余曲折はあったが、現在の育児院には2歳から18歳までの男女86人が暮らし、一般家庭に近い7~8人程度の小規模な生活形態をワンセットにしている。小中高生や男女が混じる“一つのホーム”には、決まったスタッフ(保育士や児童指導員)が朝2人、夜2人ずつ担当している。
生活の場には必ず台所がある。担当スタッフが毎日2~3食、そこで調理する。1日の食費は子ども一人当たり900円。担当者が自分で材料を買ってくる。ある部屋を訪ねた。
今春大学を卒業してここに就職したばかりの男性保育士が、台所で夕食の準備をしている。
「学生時代は料理はしたことはなかったけど、先輩に聞きながら、いろいろ作れるようになりました」と手つきもまずまず。

入所1年目の男性保育士も台所で料理を作る
専門の栄養士からメニューの指導を受けつつ、子どもたちに「何食べたい?」と希望を聞く。そうすると食べ残しも少なくなり、残っても翌日温めて食べる、といった一般家庭と同じサイクルになる。台所で自分の弁当を作って持っていく高校生の女子もいる。
さらに、「小規模化」を一歩進めて「地域に出ていく」方策も進めている。2000年から取り組みを始めたグループホーム(地域小規模児童養護施設)で、現在「かりんの家」と「ひまわり」の2施設がある。施設外のアパートや一戸建てを借りて生活を共にする。
施設から歩いて5分ほどの「かりんの家」を訪ねた。藤田毅・副園長(47)と職員で妻の直子さん(40)が小中高生(9~17歳)男女5人と住んでいる。
「小集団の子どもと向き合うのは、施設内よりも3~5倍の労力がかかる。でも、人(職員)の顔が変わらない環境で起居を共にする生活は、安定した関係を維持できて丁寧な子育てができる良さがあります」と効果を口にする。
一方、子どもたちの成長もあるという。「わずかな距離であろうと、施設から離れた場所で生活すると、そこから学校へ行き、日ごろは周辺の地域の人たちと話したりする。それは子どもを大人へと成長させる大きな要素です。施設の中では得られないものがたくさんあります」
3・11東日本大震災に襲われたとき、子どもたちは施設に避難せず、近所の住民と一緒に公的施設に避難したという。「施設の子」でなく、「地域の子」という意識が育ったのか。
勤続25年の藤田副園長は若い職員を育てる立場でもある。先輩から厳しくも温かく鍛えられた自身の経験から、「この仕事の面白さを一番に伝えたい。子どもとしっかり向き合えば必ず自分が成長する。今の若い人は失敗を恐れるが、僕ら先輩が責任取るから安心して失敗させてあげる態勢にしたい」と若いスタッフに期待する。
【網谷隆司郎】