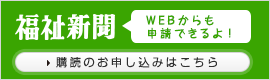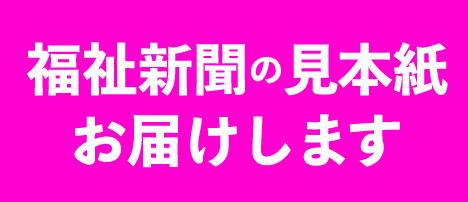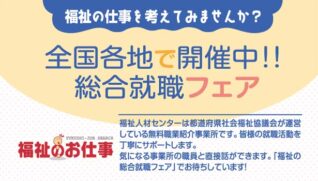社会福祉法人風土記<16>大館感恩講 上 民間主導の窮民救済の先駆け
2016年10月03日 福祉新聞編集部
次々と投げ込まれた餓死者の山が川の流れをせき止めるほどになり、全国各地で親子心中や村ごとの集団自殺が相次ぎ、果ては人肉を食らう地獄絵図まで現出した、と伝えられる江戸三大飢饉の一つ、「天保の大飢饉」。
そこから感恩講は生まれた。秋田の感恩講は、日本での民間主導の窮民救済事業の先駆けであり、今でいう福祉NPO第1号と称される。
天保4~10(1833~39)年に続いた大飢饉は、とりわけ出羽国、陸奥国といった北東北で深刻だった。大雨、洪水、冷害によって大凶作となり、疫病(腸チフス)の蔓延が悲劇に拍車をかけた。
この惨状を目の当たりにした秋田・佐竹藩の御用商人、那波祐生は飢餓に苦しむ人々を助けようと、自ら金四百両を差し出し、有力町人衆にも協力を呼び掛けて救済資金をかき集め、窮民たちに食料を与えた。財政が火の車状態の藩に頼らず、一般町民にまで献金の輪を広げた、完全民営の救済事業組織ができ、「感恩講」という名が付けられた。
その慈善の輪はじわじわと周辺に広がり、当時田畑が広がる大館にも伝わった。肝煎という、当時の村落共同体のリーダーだった石田宗右衛門が音頭を取って窮民救済を次のように呼び掛けた。
「天保4年の飢饉の惨状を思い起こすと、あまりのむごさに今でも身震いがする。しかし、今後二度とあのような目に遭わないという保証はない。だから今後、飢饉、疫病があっても人々を救済することのできる方法を何とか考えていこうではないか」
天保11(1840)年正月の御用始めの席に集まった豪農、地主たちも賛同した。それぞれが寄付金を出し合い金利運用とともに田畑を買い増して安定基金として、蔵を建てて籾を貯蓄した。
特徴的なのは、所有した田畑の名義人を個人名にせず、「田畑をもって郷人を助ける」趣旨から擬人名の「田畑郷助」とした点だ。始めから一種の法人組織として大館感恩講はスタートしたのだ。現在の社会福祉法人「大館感恩講」の起点はこの年であり、今年で創設から176年を数えた。
その後、幕末から明治にかけて、戊辰戦争などによる混乱の中、大館も戦場となり、大半の地域が焦土と化した。だが、「田畑郷助」は備蓄米を供出して窮民を救った。「国破れて何の貯蓄ぞ。非常の際に役立ててこその貯蓄ではないか」の心意気だった。
文明開化を標榜した明治新政府は、近代国家樹立のため、欧米の法制度を取り入れ、フランス人・ボアソナードが起草した民法が明治31(1898)年施行された。それまで任意団体だった「田畑郷助」も、時代の要請で明治32(1899)年、「財団法人大館田郷感恩講」として再スタートした。田郷はもちろん田畑郷助を省略したものだ。
財団法人の定款に当たる「条規」はボアソナードの校閲を受けた秋田感恩講のものを模範にして決めた。唯一の目的を「窮民救助」とし、対象者は町内に住む一人暮らし、身体障害者、知的障害者、困窮家族と定め、大人1日2合6勺、小人1合3勺の米を給与するのを原則とした。さらに生活・医療・生業扶助も行うとした一方、それぞれの自立努力を期待するという趣旨を入れるなど、全31条に及ぶ詳細な内容だった。
明治33(1900)年の実績記録が残っている。町内の13戸22人に米10石5升1合6勺を与えたほか、1年間で延べ4211人(大人3521人、小人690人)を救助したという。
大正、昭和と時は過ぎるうちに、行政側の福祉への動きも目立ってきた。現在の民生委員の前身、方面委員が秋田県でも昭和2(1927)年活動を開始していた。そこから思わぬ批判が出た。
「感恩講は消極的な事業しかしておらず、現在のままでは宝の持ち腐れだ。資産を町に返還すべきだ」と事実上の解体を迫ったのだ。感恩講の理事が反論し存続を保ったが、これを機に条規を改正して救済対象者を町内居住3年から2年に改め、より多くの窮民救済を図った。
だが、昭和20(1945)年8月の終戦とその後の日本社会の大変革が、大館田郷感恩講の屋台骨を揺さぶることになった。
【網谷隆司郎】