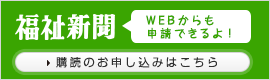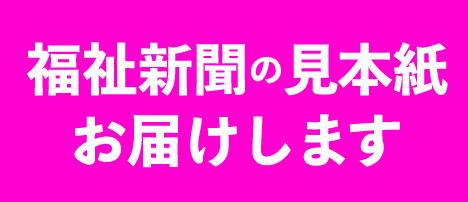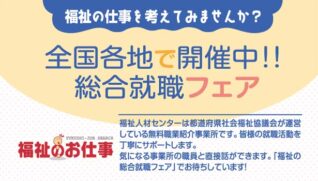社会福祉法人風土記<12>弘前愛成園 下 原点は五三郎の人間愛
2016年06月20日 福祉新聞編集部
社会福祉施設は社会を映す鏡と言える。その時代その時代でさまざまな姿に変わる。困窮と悲劇の現実から、子ども・障害者・老人を救い、体と心の元気再生、生きる力が湧き出てくる手助けをすることに変わりはないが。
1902(明治35)年の誕生から明治、大正、昭和、平成と活動を続けて、今年創立114年を迎えた、日本有数の伝統を持つ社会福祉法人「弘前愛成園」も、時代と共に、その姿を変えてきた。
町の小さな薬屋だった佐々木五三郎が私財を投げ打って6人の孤児救済から始めた社会事業は、「自働自営」の旗印の下、映画館の興行や戦後の病院経営による財政基盤の健全化を果たした。「青森県初の」という枕詞が付く児童養護施設・養護老人ホーム・特養ホームが示すように、先進的な取り組みが多い。行政との連携も進み、デイサービスやグループホームなど各種福祉サービスを増やしてきた。カラオケ、ダンスなどサークル活動やボランティア活動を通して、施設内の人間関係にとどまらず、地元の高齢者や子どもたちとの絆も太くした。
だが、日本社会は1980年代から激動した。世界有数の少子高齢社会への進み具合が、家族の在り方を変え、従来の福祉政策と制度を次々と改変させた。全国の福祉施設が動揺した。

父の肖像画の前で三浦昭子理事長
社会も制度も施設も揺れ動く1996年に社会福祉法人「弘前愛成園」の4代目理事長に就任したのが三浦昭子・現理事長(77)だった。愛成園を作り育てた佐々木五三郎、その娘婿の佐々木寅次郎・三浦昌武が築いた伝統の重さを感じつつ「神輿がなくては事業はうまくいかない」と大任を引き受けた。
熱血教師だった父・昌武の血を引いたか、昭子は施設長を40歳代の職員に任せるなど幹部職員や理事の若返りといった新時代への対応策を断行した。だがそれには古参職員からの「お父さんはそうはしなかった」という抵抗に遭った。
「それまでの措置制度に固まった職員からは創意工夫は出てこなかった。介護保険など制度が大きく変わった以上、その中で利用者のために何をしたら一番いいか、若い人たちに創意工夫をしてもらいたかった。時代の切り替えが必要でした」とトップダウンの真意を語る。
時代の激変は入所者たちの動機や姿も変え、職員の対応も変わらざるを得なくなった。
例えば、児童養護施設「弘前愛成園」では、飢餓児童や戦災孤児という時代相はなくなり、近年は親の虐待による入所動機が多くなっている。
加藤敬記園長(64)、佐藤優輝次長(37)、外崎了次長(42)によると、親自身の精神疾患による虐待やネグレクトによって傷ついた児童には、罰を与えてルールに従わせよう、矯正しようというやり方を変えて、じっくり関係性を築いて、「自分は大切にされている」という思いを持たせることが大切だ、という。
かつてのように非行で警察から呼び出されるケースが減った代わりに、心の病で病院に付き添うことが増えた。不登校の児童には学校の先生との情報交換を密にして、先生が愛成園に来るなどソフトな対応を目指している。
養護老人ホーム「弘前温園」でも、権利意識が強く、「好きな時に酒が飲みたい」「マイカーを持ってきたい」など多様な要求をする入所者が増えた。

土岐浩一郎施設長(左)と照田英明園長
「原点は五三郎の人間愛で対応します」という土岐浩一郎施設長(51)は、「現場の職員が粘り強く受け止めてくれている。よく頑張ったねと誉めることもある。それに、うちは法人として墓を持ち、最後までお世話するという良さがあります。僧侶が定期的に園内に読経に来てくれるなど、長い歴史の中で市民と共に歩んできた強さがあります」と語る。
特別養護老人ホーム「弘前静光園」の照田英明園長(59)も「うちも看取りが主になった」といい、「重度化が進み、介護職員に求めるものが高くなった。介護リフト、全身サポート、赤外線センサー導入で負担減を計る一方、何とか自分たちの工夫・改善で働きやすい職場、笑顔のあふれる職場づくりを目指しています」と、特に若い職員のモチベーション維持に力を入れる。
少子高齢社会が福祉施設に及ぼしたさまざまな現実と課題に“平成の五三郎たち”が向き合い模索している。
【網谷隆司郎】