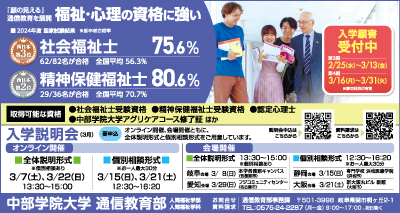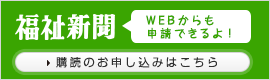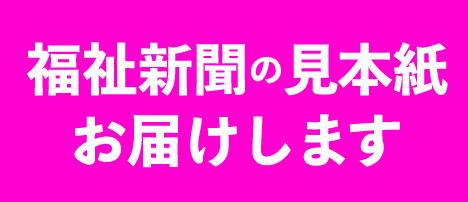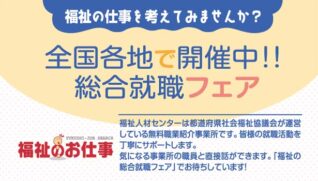社会福祉法人風土記<6>愛友園 戦後編 上
2015年10月22日 福祉新聞編集部
戦時中のニコルソンは、強制収容された日系人のために身の危険も顧みず、強制収容の不当性を訴え、全米の収容所を慰問に訪れ、日系人の権利擁護のための陳情活動などに奔走した。終戦を迎え、日本の食糧難を知ると日系人をはじめとしてクエーカーのフレンド会、カトリックなど各宗教団体などが組織的に救援物資を送ろうと動き出す。1946(昭和21)年4月に設立された「アジア救援公認団体」(略称ララ、代表の1人がクエーカーのエスター・ローズ)が物資の輸送・分配に当たることになった。ニコルソンもヤギを送るプロジェクトを担い、ヤギと共に貨物船に乗り、最初は沖縄に、1948(昭和23)年5月、2度目のヤギ輸送の船で横浜に上陸した。この時のエピソードが脚色されて小学校の教科書に掲載されて“やぎのおじさん”として知られるようになった。
原爆投下をわびる
「水戸は自分の故郷」とまで言っていたニコルソンだが、原爆投下のおわびをするために広島市長、長崎市長を訪問したほか、結核患者やハンセン病患者を見舞うため、各地のサナトリウム、国立療養所などを訪れた。さらに、死刑囚を慰めるために刑務所も訪問するなど忙しく活動、すぐには水戸に帰れなかった。
やっと水戸に戻ったのは、1950(昭和25)年4月。戦災で市街地の85%もが焼けていたが、自宅や施設があった東原に来てみると、幼稚園と労働者住宅は焼けていたものの、住宅と紫苑寮は、奇跡的に焼け残っていた。住宅には4発の焼夷弾が落ちたが不発だった。ホームには8発も落ちたが、7発は不発で、発火した1発も施設を守っていた島村卯之助寮長が布団をかぶせて消した。
それにしても荒れ果てた寮や住宅には職員家族や避難民であふれかえっていた。戦中、戦後の混乱期は、クエーカーの日本人信者らが施設の運営にあたったが、資金が枯渇し、閉鎖が議論されたこともあった。しかし、「ニコルソンさんが帰ってくるまでは」を合言葉に頑張ったという。「食糧難時代は、農業をしていた信者たちが作物を持ち寄ってくれたので、みんなで分けあったようです」と愛友園監事の人見守さん(85)は語る。
戦後になってからは、アメリカのクエーカーから援助物資が届き、共同募金の配分があり、そこへニコルソンが帰還したことで、危機を脱した。困難な時期を乗り切った島村寮長が1948(昭和23)年に死去したものの、ヤギと鶏を飼育しながら酪農場を守っていた山口晋が病気を克服して島村寮長の後継者として働き始めた。その後、新憲法のもとで社会福祉制度も変わり、1953(昭和28)年に紫苑寮は社会福祉事業法に基づく社会福祉法人「愛友養老園」として認可され、山口晋が園長になった。
かつて、ヤギの乳を子どもたちのために提供した縁で知り合いになった水戸市内の実業家が援助を約束してくれたこともあり、ニコルソンは施設を改築するための資金集めに奔走し始めた。
法人の理事長はニコルソンが、施設の運営は山口園長に任せられていたが、法人の経営主体はクエーカーの信者組織のフレンド日本友会だった。法人の理事長だったニコルソンがアメリカに一時帰国した後の1955(昭和30)年から3年間はララ代表で、普連土学園理事長でもあるエスター・ローズが就任したこともあった。
二人三脚で奮闘
「やぎの大使・悲しむ者みなに慰めを」(ハーバート・ニコルソン著)によると、ニコルソンは、1962(昭和37)年に米国へ帰国するまでの最後の4年間は水戸に住んだ。その4年間についてニコルソンは「施設の主幹者として山口晋さんが、耐火性の建物を作り上げる作業や、施設の中にキリスト教精神を生み出すための手伝いをしました。資金を生み出すために県の福祉事務所、東京の共同募金にお願いしました。寄付金を戴くために水戸の銀行、事業団体、個人にもあたりました」と記述している。ニコルソンと山口晋は、施設を80人規模にするために二人三脚での奮闘だった。
その後、介護保険制度に変わる過程で、2000年からは、山口晋園長が理事長職に就き、施設長も兼務するようになった。
(若林平太)
関連記事
関連書籍
税務経理協会
売り上げランキング: 59,416
税務経理協会
売り上げランキング: 91,342