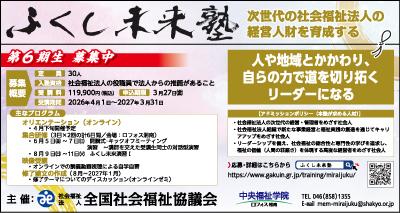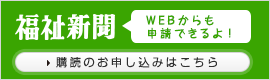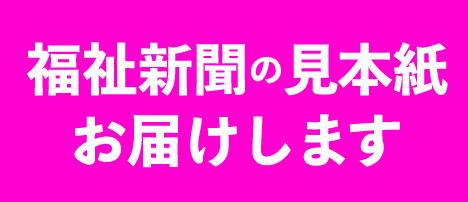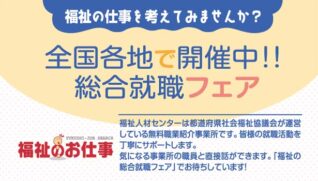【淑徳大・中】辛苦を支えるものたち
2026年02月04日 福祉新聞編集部
社会改良を目指すセツルメント「マハヤナ学園」の事業は年々拡大していく。そのさなか、園長・長谷川良信(1890~1966)=淑徳大学創立者=は、1922(大正11)年3月から1年半ほど、浄土宗海外留学生兼内務省嘱託として外遊している。
米シカゴ大学社会事業科で半年、さらに欧州へ渡り、独ベルリン女子社会事業学校に籍を置いて教授に師事。「アメリカ型の機能的社会事業と、ドイツ型の社会政策をともに吸収しようとした」(『淑徳大学十年史』)。大正大の学生として良信に教えを受けた社会福祉学者、吉田久一・元日本社会事業大教授はこう評価する。大正大は天台宗大学、豊山大学、宗教大学が連合し26年にできた仏教教育の館だ。

マハヤナ学園の児童倶楽部=1920年
ところが関東大震災(1923年)の報に急きょ帰国へ。途次、風邪をこじらせ入院しながらシベリア鉄道経由で東京府・西巣鴨へ戻ったのは、その年12月であった。園は惨状の都心を脱する人々の一時避難所になっている。
良信は再興に着手する。宗教大学教授に就任した24(大正13)年、欧米での知見をもとに女子の地位向上と淑(きよ)き婦徳を持つ良妻賢母の養成に向け「大乗女子学院」(夜間)を開校。翌年には「巣鴨家政女学校」と校名を改め、実業教育に乗り出した。さらに31(昭和6)年、「聡明快活」を校訓とする「巣鴨女子商業学校」(いまの淑徳巣鴨中高校の前身)へ衣更えするのと同時に、組織を「大乗学園」の名で財団法人化している。
ここに多忙な良信を一途に支えた2人の女性協働者が登場する。若くして世を去った先妻りつ子(1899~1935)、彼女を姉と慕った後添えのよし子(1907~96)だ。二人の出会いは、東洋大社会教育・社会事業科(夜間)学生のよし子が園で実習する32年のことだった。ふるさと静岡県での高等女学校教諭を辞したりつ子が、見合い相手の良信と結ばれてすでに7年の歳月が流れていた。

長谷川りつ子

長谷川よし子
マハヤナ学園は本館・別館のほか、33年までに千葉県と東京に四つの保育園などを運営。このはざまに、欧米の政治や労働事情に対する知識を買われ日刊新聞「万朝報」主筆としてロンドン軍縮会議に随伴し3カ月ほど英独米を視察(30年)したり、財政難打開を掲げる全日本私設社会事業連盟(事務局・マハヤナ学園)の旗揚げ集会(大阪、31年)、育った得生寺(茨城県)の23世住職就任(32年)、巣鴨女子商業学校の初代校長を引き受けてくれた恩師・渡辺海旭の逝去と自らの校長就任(33年)と、矢つぎ早に公私の仕事を増やしていく夫に、りつ子は黙々と伴走した。
「幾分なりとも社会悪を取り除くことが出来得ましたら、私達は本当に満足だと存じます」
万朝報記者のインタビュー(30年)にこう応じつつ、台所は火の車の園を統括した。その激務から脊髄カリエスを発症。薬石効なく、37年の生涯を閉じてしまう。
りつ子の遺志を継ぐかのように翌年、出身の愛知県で少年保護司をしていたよし子が良信の申し出を受け、この世界へ。3人の養親を転々とした向学心あふれる尼僧(浄土宗尼衆学校卒業)は還俗し、機能しない社会事業法(1938年施行)と、戦時色が日々強まる私設福祉事業の〝冬の時代〟にあって、マハヤナ学園を切り盛りした。戦後も4人の子を育てながら、ブラジル開教(サンパウロに日伯寺建立・日伯寺学園設立、57年)にかける夫(53~62年に3度渡伯)を見守り、社会福祉法人となった学園の児童養護施設「撫子園(なでしこえん)」の施設長(58年)や、良信没後には中高校長(66年)として母性教育にまい進した。
撫子園は50年に巣鴨から現在の板橋区へ移転。そのころ一帯は工場や田畑がバラバラに点在していた。
社会福祉学者の一番ヶ瀬康子・日本女子大名誉教授(1927~2012)は、社会事業に関わる女性には三つのタイプがあると言う。創業者として活躍した人、報いを期待せずひたすら下支え役に徹した最も地味な人、そして事業に打ち込む夫の「妻」「共働者」を生きた人。第三のタイプを次のように描く。
「(第一、第二)両方のタイプの女性がもっているそれぞれの悩みと苦しみをともにかかえつつ……強靭な力と柔軟性、またみちあふれるような心情の豊かさが、より以上に要求されているのではないだろうか」(五味百合子編著『社会事業に生きた女性たち』ドメス出版)。
りつ子、よし子を指しているかのようだ。
ところで教え、支える側もまた支えられる。2年ほどマハヤナ学園主事として教べんをとってきた前述の吉田久一は43(昭和18)年に召集された。その送る会。
「送別の言葉を述べてくれたのは、私がもっとも手を焼いた生徒であった。別れの悲しみをこえて、明らかに彼女達に、私が去った後の学校を守り抜く決意が溢れていた。この夜の別れが、足かけ四年の中国から沖縄戦争従軍に、どれほど支えとなり勇気づけられたことか」(著作集7『太平洋戦争下の生徒たち』)
「共生(ともいき)」の心はここにも脈打っていた。